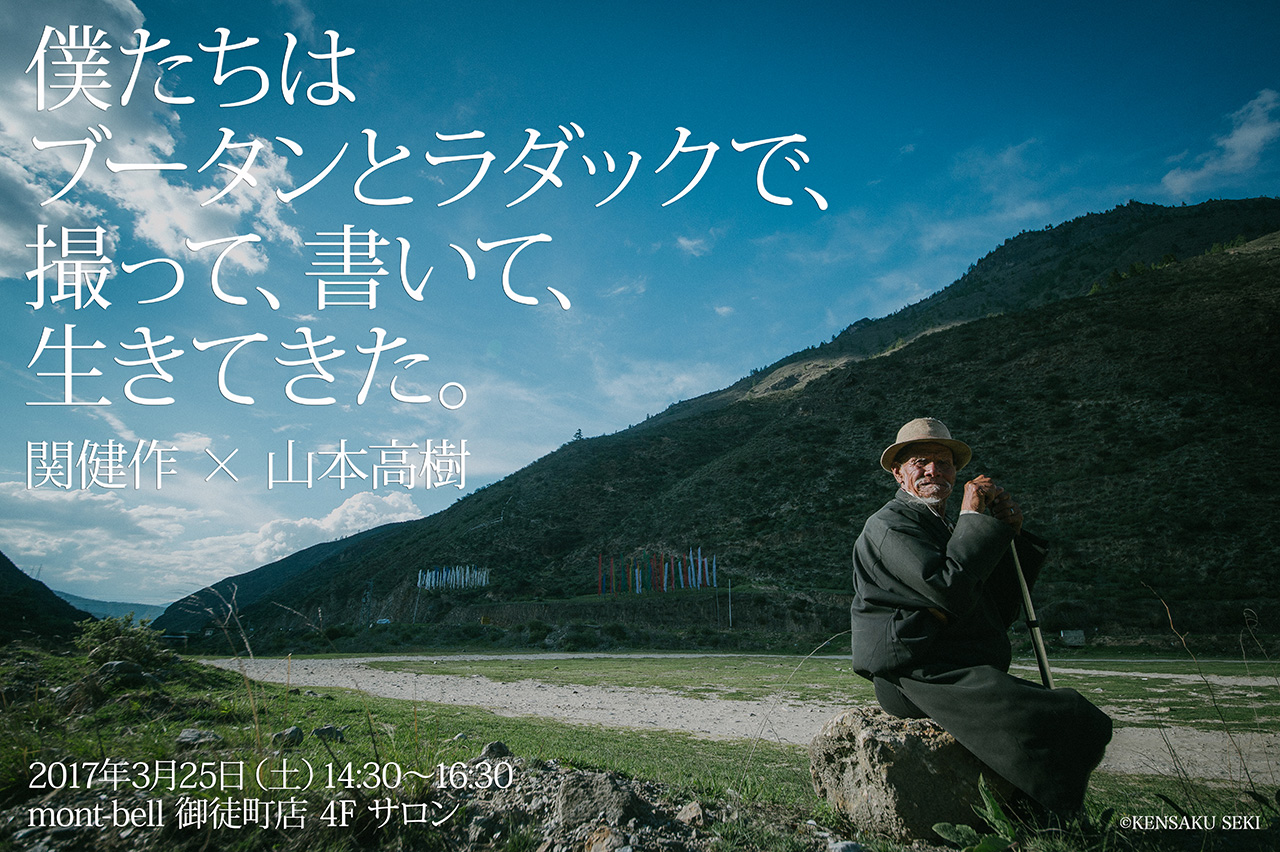一昨日の「旅の本づくり」をテーマにしたトークイベントの時、自分の作りたい本の企画書をわざわざ用意して、僕に相談しに来た人が何組もいた。実際、すでにいくつかの出版社に持ち込んだ人たちもいたのだが、「あなたの代わりに、かわいいタレントの女の子にレポートさせたら?」とか、「100万円持ってきたら、自費出版扱いで作ってあげますよ」とか、いろんなことを言われているという。
僕自身、自分の本の企画を出版社に持ち込んだ回数はかなりの数になるが、ひどい対応をされて嫌な思いをした割合の方が、圧倒的に多い。出版社の知名度や規模に関係なく、編集者にもいろんな人がいる。はっきり言うと、人格的にも能力的にも、ピンからキリまでいる。写真がメインの企画なのに、最初から最後まで一人で適当にしゃべり続けて、一枚も写真を見ようとしなかった人。アポイントを仮病でドタキャンしてリスケもしなかった人。電話とメールで丁寧に打診したのに受領確認の返信すら寄こさない人などは、星の数ほどいる。
本を出したいと考える人の中にも、名前を売りたいとか、ハクをつけたいとか、商売に利用したいとか、そういう邪な動機の人もいるとは思う。企画自体が致命的な弱点を抱えている場合もあるだろう。ただ、自分の本を作りたいと出版社に企画を持ち込む人の多くが、どれだけの熱意と思い入れを持って、勇気を振り絞って門を叩いているか。僕にはその気持ちが、痛すぎるほどよくわかるのだ。
だから、出版社側の編集者は、熱意と思い入れと勇気を持って門を叩いてきた人に対して、きちんと誠意を持って対応すべきだと思う。もちろん、企画に弱点があれば、ばしばし指摘してしまっていい。本にするのが難しければ、正直にそう伝えるべきだ。でも、本の企画を持ち込んだ人の熱意や思い入れを上から目線で嘲笑ったり、無責任な言動で傷つけたり踏みにじったり、あるいは企画の打診そのものを無視したりするようなことは、絶対にしてはならない。それは編集者云々以前に、社会人として、人として、当たり前のことだ。