 この夏、成田とデリーを往復するエアインディアの機内では、本当に一睡もせずに(笑)インド映画をかたっぱしから観まくった。最初に観たのは、昨年末インドで大ヒットした「Happy New Year」。シャールクとディーピカ、監督ファラー・カーンという「Om Shanti Om」以来のトリオに加え、脇役陣もアビシェークをはじめとする豪華な顔ぶれ。撮影の多くはドバイロケという、ものすごく贅沢な造りの作品だった。
この夏、成田とデリーを往復するエアインディアの機内では、本当に一睡もせずに(笑)インド映画をかたっぱしから観まくった。最初に観たのは、昨年末インドで大ヒットした「Happy New Year」。シャールクとディーピカ、監督ファラー・カーンという「Om Shanti Om」以来のトリオに加え、脇役陣もアビシェークをはじめとする豪華な顔ぶれ。撮影の多くはドバイロケという、ものすごく贅沢な造りの作品だった。
賭けボクサーに身をやつしていたチャーリーは、クリスマスにドバイの巨大金庫に希少なダイヤモンドが運ばれてくるというニュースを目にする。その金庫のセキュリティを担当するグローバーは、かつてチャーリーの父を罠にはめて現在の地位にのし上がった男だった。チャーリーは復讐のために仲間たちを集め、ドバイの金庫からダイヤモンドを盗み出す作戦を画策。しかしその作戦を成功させるには、ドバイで開催されるワールド・ダンス・チャンピオンシップにインド代表として出場しなければならない。彼らはポールダンサーのモーヒニーの下でダンスの特訓を開始するが‥‥。
作品の印象は、良くも悪くもファラー・カーンらしい映画という感じ。ダンスシーンは華やかだし、ストーリーもわかりやすくて盛り上がる。その一方で、それはちょっと余計なんじゃないかという冗長な部分も結構目に付いて、あと20分は編集で削れたんじゃないかと思えるほど、造りはユルい。まあでも、こういう頭をカラッポにしてスカッと楽しめる、典型的なボリウッドの娯楽大作もあっていいと思うのだ。現代的に洗練された作品ばかりでもつまらないし。
細かいツッコミどころは満載だけど、それも含めてたっぷり楽しめる作品だ。長いけど(笑)。

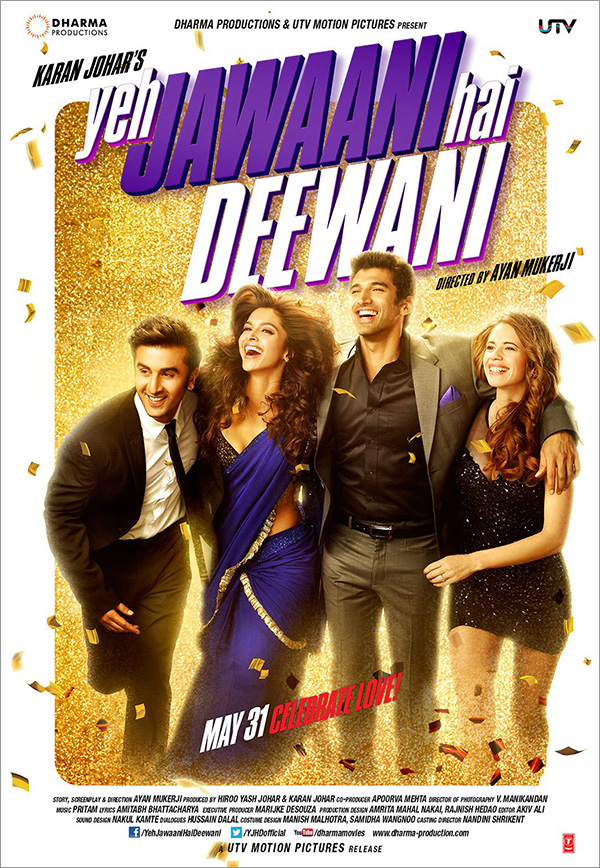 日本の映画館のスクリーンで観ることを長い間待ち焦がれていた作品を、ついに目にすることができた。「
日本の映画館のスクリーンで観ることを長い間待ち焦がれていた作品を、ついに目にすることができた。「 先日のノルウェー取材の時に乗った飛行機では、なぜかインド映画のラインナップが充実していた。ミュージカルシーンがばっさりカットされた残念なものも多かったのだが、この「
先日のノルウェー取材の時に乗った飛行機では、なぜかインド映画のラインナップが充実していた。ミュージカルシーンがばっさりカットされた残念なものも多かったのだが、この「
