3月11日。東日本大震災が起こってから、一年が過ぎた。
一年前のこの日、凄惨な光景が映し出されるテレビの映像を見ながら感じていたのは、「またか」という思いだった。その半年ちょっと前の2010年8月に滞在していたラダックでは、集中豪雨による洪水で600人以上の命が奪われていた。僕は、トレッキングで訪れていた山の中で、濁流に呑まれそうになりながらも命からがら生き延びたのだが、その後は土石流で変わり果てた被災現場の写真を撮って、日本に送ることくらいしかできなかった。自分にとってかけがえのない場所や人々を襲った悲劇を目の当たりにした時の無力感とやりきれなさ、情けなさは、胸の奥にこびりついたままだ。震災の映像を見た時、その感覚がまざまざと甦った。
東北や北関東の被災地に比べれば、当時の東京の状況はどうということはなかった。計画停電なんて、ラダックは無計画停電が当たり前だし(苦笑)、菓子パンを買い占めたところで、食べ切れずに腐らせるだけだし。自分自身については、必要な用心さえしていれば何とでもなる、と開き直っていた。ただ、自分が被災地の人々に対して何か効果的なことができるのかと考えると、ラダックの洪水の時と同じ無力感に苛まれて、暗澹とした気分になった。
震災から数カ月後、父が急に逝ったことも、僕と家族にとっては大きな打撃だった。去年の初め頃から実現を目指していたラダックのガイドブック企画も、こうした想定外の出来事でたびたび頓挫し、ほとんど諦めかけた時期もある。そんな僕を奮い立たせてくれたのは、日本で、ラダックで、僕を支えてくれたたくさんの友人たちだった。
ラダックの洪水や東日本大震災の時から感じていたあの無力感は今も消えないけれど、自分が選んだ生き方の中で、自分にできること、やるべきことを一つずつ積み上げていこう、という気持にはなれた気がする。僕にとって、それは本を作ること。それしか能のない役立たずだけど(苦笑)、やるしかない、と。
みんながそれぞれの人生の中で、できることを精一杯やっていれば、きっと誰かに繋がる。今はそう信じている。

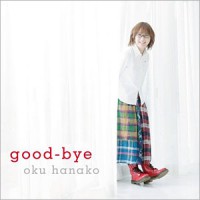 奥華子のメジャー通算六枚目のアルバム、「
奥華子のメジャー通算六枚目のアルバム、「