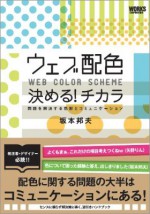この間の、西村さんと夏葉社の島田さんの公開授業で出ていた話題の一つについて。
授業を受けていた学生さんが、「自分がやりたいこと、好きなことに取り組んでいきたいけれど、それで食べていけるのかどうか不安になります。どうすればいいのでしょうか」という質問をした。確かに、美大の学生さんともなると、自分の作品づくりを生活の糧にできるかどうかというのは、重要な課題なのだろう。
それに対して西村さんは、「たとえばバイオリンを学んだ人が、普段は他の仕事をしながら、週に一度仲間内で集まって演奏をして、何年かに一度、どこかでコンサートを開く。そういう取り組み方もある。好きなことをするなら絶対にそれで食べていかなければダメだ、というわけではないと思う」と指摘した。確かに、それはその通りだ。
好きなことをすることと、それで食べていくということは、必ずしも結びつける必要はない。絵画や音楽、文学などの分野で素晴らしい才能を持ち、世間的にもきちんと評価されている人が、普段はまったく別のことをして生計を立てている例はいくらでもある。それで食べていけないからといって、好きなことへの取り組みをすべてあきらめてしまうのはもったいない。
ただ、意地でも自分の好きなことをして食べていく、という覚悟で取り組んでいる人には、退路を断った人ならではの気迫と集中力が宿るのも確かだと思う。勝ち負けの問題ではないけれど、他の仕事で生計を立てながら好きなことへの取り組みを続けるのは難しい面もある。結局大事なのは、それで食べていけるかどうかではなく、自分が好きなこと、やりたいと思ったことを、とことん最後までやりきれる覚悟を持てるかどうか、なのだろう。
僕自身、好きなことをして食べていけている状態と言えるかどうか、微妙なところだと思う。ライターや編集者としての仕事全般では、まあ、かつかつ。自分が好きな旅にまつわる仕事に限ると、まだまだ。でも、自分がやってみたいこと、好きなことに取り組むには、今のフリーランスの状況に身を置いておくのが一番やりやすいし、実現の可能性が高い。だから僕は、これからもやせ我慢を続ける。
好きなことをして、それで食べていく。楽なわけないよね。