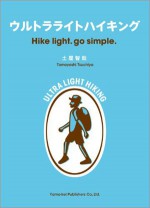 僕が住んでいる三鷹に、ハイカーズデポという小さなアウトドアショップがある。駅の南口から歩いて15分ほど、デイリーズが入っているのと同じビルの一階。たしか、2008年の秋、僕がラダックでの長期取材から戻ってきたばかりの頃にオープンしたんじゃないかと思う。
僕が住んでいる三鷹に、ハイカーズデポという小さなアウトドアショップがある。駅の南口から歩いて15分ほど、デイリーズが入っているのと同じビルの一階。たしか、2008年の秋、僕がラダックでの長期取材から戻ってきたばかりの頃にオープンしたんじゃないかと思う。
僕自身は、そんなに足繁くハイカーズデポに通って買い物をしていたわけではないのだが、他の店とはひと味違った、シンプルで軽快なウェアやグッズの品揃えは、前々から気になっていた。店主の土屋さんもアウトドア雑誌でよく見かけるようになり、先日、ついに「ウルトラライトハイキング」という本まで出されたのを知った。
ウルトラライトハイキングとは、アメリカの数百キロから数千キロに及ぶロングトレイルを踏破するスルーハイカーたちによって考案されたハイキングの手法だ。装備を徹底的に軽量化し、必要なアイテム数を最小限に絞り込むことで、装備を背負う身体にかかる負担を減らし、長い距離を快適に歩き続けることを目指しているのだという。
日本でこうしたテーマについての本を作ろうとすると、ウェアやグッズをずらずらと紹介するものになってしまいがちだが、この「ウルトラライトハイキング」は、そうしたカタログ的な本とは一線を画している。ウルトラライトハイキングとは、最新のハイテク素材で作られたおしゃれなグッズを揃えて悦に入ることではない。工夫を凝らしたシンプルな装備で山に分け入って、自然とのかかわりや一体感をよりダイレクトに感じ、愉しむという行為なのだ。この本ではウルトラライトハイキングについてのそうした考え方とともに、実践にあたっての基本的な知識が、わかりやすい形で紹介されている。ふんだんに添えられたポップなイラストも感じがいい。
僕がラダックでトレッキングをくりかえしていた頃は、装備と食糧は馬やロバに運んでもらっていたものの、自分自身は撮影機材が詰まったカメラバッグをひーこら言いながら担いでいたので、とてもウルトラライトとは言えなかったと思う(苦笑)。でも、現地で旅をともにしたホースマンたちの装備の潔さにはいつも感心させられていたし、厳寒期のチャダル・トレックに臨む前、友人のパドマ・ドルジェに「テントもストーブも必要ない」とこともなげに言われた時には度肝を抜かれた。ラダックやザンスカールの人々にとって、最小限のシンプルな装備で旅をすることは、日々の生活に直結したごく当たり前の知恵なのだけれど。
もう少しいろいろ落ちついてきたら、ひさしぶりに丹沢や奥多摩、奥秩父を歩いてみようかな。自分にできる範囲で、ウルトラライトに。
