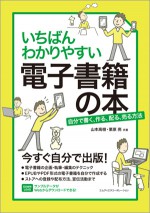今日は、一念発起。昨日のエントリーにも書いた、置き場のなくなった本や雑誌の処分に着手。
本棚や押し入れの中から、いらなくなった本を選り分けていく。愛着のある本も多いのだが、その一方で、仕事の資料として買ったり送ってこられたりした後、その役割を終えた本も少なからずある。そういう不要なものをまとめていくと、ダンボール箱二つ分になった。うちの近所、五日市街道沿いにあるブックオフまで、ずっしり重い箱を抱えて二往復。ひさびさの肉体労働に、腕の筋肉がぷるぷるする(笑)。買取価格は思ってたよりもよくて、2800円ちょっと。スライド書棚も数十冊分のスペースが空いたので、ほっとひと息。
その後、夕方に新宿で友人と会う約束があって、出かける。新宿に着いて、待ち合わせ時間までちょっと余裕があったので、ジュンク堂にふらっと入って‥‥あれ? どうして新しい本を二冊も手に‥‥?
本を売った金で、本を買う。これじゃ、いつまで経っても抜け出せないな(苦笑)。