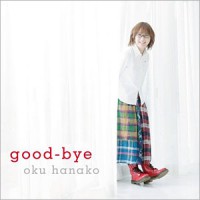 奥華子のメジャー通算六枚目のアルバム、「good-bye
奥華子のメジャー通算六枚目のアルバム、「good-bye」。このアルバムは本来なら、去年の秋くらいには出ているはずのものだったと思う。先行シングルの「シンデレラ
」は、去年の六月に発売される予定だったが、半年以上延期された。その原因には、東日本大震災がある。
震災後、彼女はそれまで予定されていたリリースプランを変更し、被災地を支援するための活動に奔走した。「君の笑顔 -Smile selection-」というコンセプトアルバムを作り、全国各地でフリーライブを開催して支援金を募り、被災地にも何度も足を運んで、歌った。そんな中でも、たぶん、彼女は痛いほど感じていたと思う。想像を絶する現実と悲しみの前で、自分たちがどれほど無力なのかということを。
去年、彼女は南三陸町の避難所で出会った女性から、「頑張ろうとか、応援歌とかではなく、行き場のない思いに寄り添った曲を作ってほしい」というメールを受け取った。「頑張れと言われても、頑張りたくても、なかなか頑張れないんです」と。自分が経験したのではないあの悲劇について、何が歌えるのだろう。でも、その思いを教えてもらって歌にすることはできるかもしれない。そうしてメールのやりとりを重ねた中で生まれたのが「悲しみだけで生きないで」という曲だった。
本当に大きな悲しみの前では、どんな慰めも、励ましも、何の役にも立たない。その無力さも、やりきれなさも、いたたまれなさも、何もかも抱え込んだ上で、彼女は声を絞り出して歌う。「それでも生きて」と。
一人ひとりが、それぞれにできることをしながら、毎日を精一杯生きていくしかない。そうすれば、何かが、誰かに届く。明日に繋がっていく。彼女はきっと、そう伝えたかったのだと思う。
