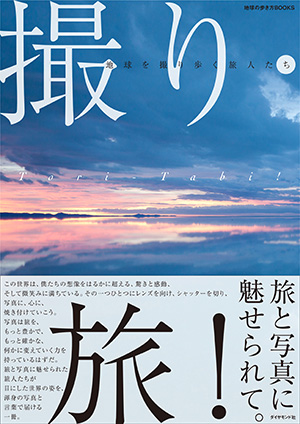ダイヤモンド・ビッグ社の「地球の歩き方」編集部のサイトで、今年二月に行ったバングラデシュの取材レポートを遅まきながら連載していくことになりました。これから十月頃(「地球の歩き方バングラデシュ」の改訂版が発売される時期)までかけて、全部で四回に分けて掲載されていくそうです。これに合わせて写真を選び直し、文章も新たに書き起こしました。サイトのデザインがやや古いため見づらく感じられるかもしれませんが、写真は一応Retina対応にしてもらっているので、ある程度はディテールも見られると思います。
タイトルは「“旅”が始まったばかりの国、バングラデシュ」。まだ観光というものが未発達な、でも、だからこそ感じることのできるバングラデシュの魅力と奥深さを、門外漢ながら伝えていければと思っています。