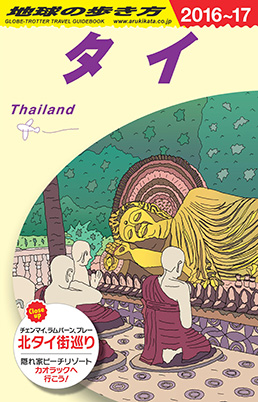今年はひさしぶりに、単独で写真展をやることにした。春先に新しい本を出すので、そのタイミングに合わせて。ここ数年、ラダック、ザンスカール、スピティで撮影してきたものを中心に、それ以前からの代表作も織り交ぜて展示しようと思っている。
会場は今のところ、2カ所を予定している。どちらも、友人が経営する飲食店の店内だ。それぞれ展示内容は異なるが、一方では約2カ月、もう一方でも約1カ月と、写真展としてはかなり長期間の展示になる。
もともとは、数年前から「次にラダックの写真展をやるなら、展示専用のギャラリーで、大きくて高画質なプリントのパネルをずらりと並べるような展示にしたい」と考えていた。メーカー系のギャラリーの公募にかたっぱしからあたってみようとか、もっと高く付くけど開催時期の調整に融通の利く私営のギャラリーはどうだろうかとか、いろいろ模索していた時期もあった。ただ、そうやって検討を重ねているうちに、なんとなく自分の中で違和感が芽生えてきていたのも事実だった。
僕はそもそも、どうして写真展をしたいんだろう? 誰に、何を伝えたいと思っているのだろう? もしかして、ただ単に自分自身の虚栄心を満たそうとしてはいないだろうか?
専用のギャラリーで高品質なパネルを並べて展示すれば、確かにそれによって伝えられる感動はあるかもしれない。でも、よほど立地条件のいいギャラリーでないかぎり、そういう展示にわざわざ足を運んでくれるのは、写真を見るのが好きな人や、すでにラダックに強い興味を持っている人にしぜんと限られてくる。期間もせいぜい1、2週間が限度だし、来たくても来れずに終わる人も少なくないかもしれない。
僕はむしろ、ラダックのことをほとんど知らない人や、写真にもあまり関心のないような人にこそ、自分の写真をきっかけにラダックに興味を持ってほしいと思っているのだ。極端な話、ヤマモトタカキが誰だとか、知ってもらわなくても構わない。この世界に、こういう場所があるのだと、ただそれを伝えたいだけなのだ。
そこまで考えがほぐれると、結論はおのずと見えてくる。今度の新しい本に合わせて写真展をやるなら、自分のルーツに一番近い場所で。誰でも気軽に来れて、何も知らずに来た人もちょっと興味を惹かれるような、さりげないけど、じわじわくる、そういう展示。それを、できるだけ長い期間、じっくりと。この世界に、こういう場所があることを、まっすぐ伝えるための写真展。
僕の伝えたいことは、たぶん、根本的なところは昔からずっと変わっていない。写真展でそれを伝えるには、少なくとも自分にはこのやり方が一番合っている。今はそう確信している。
というわけで、もうすぐ、やります。お楽しみに。