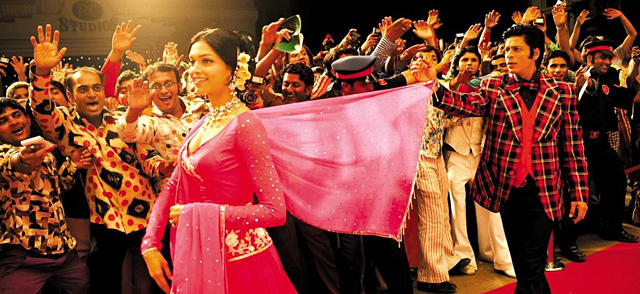実家から送られてきた野菜の中にグリーンピースが入っていたので、それを使って豆ごはんを作ることにした。
米をいつもより若干少なめにして、いつもの量の水を入れ、酒と塩を少し。ごはん鍋を火にかけて、沸騰してきたらグリーンピースを投入し、蓋をして弱火で炊き、蒸らせばできあがり。
グリーンピースはインドでは「マタル」と呼ばれていて、ジャガイモとグリーンピースのカレー(アルー・マタル)など、インド料理ではよく使われる野菜だ。インドの中でも一番上等なマタルは、スピティ産のものだと言われている。標高四千メートルに達する高地の村々で栽培されるマタルは、畑でもいでさやから取り出し、生のまま頬張っても、まるで果物のように甘い。去年の夏、スピティの村から村へと歩いて旅していた時、収穫に精を出す村人たちが、もぎたてのマタルをよく手づかみで分けてくれたっけ。
僕にとっては懐かしい、マタルの味。もうすぐ、またあそこで味わえるかな。