俳優の水嶋ヒロが書いた小説が、ポプラ社小説大賞を受賞したという。このニュースでちょっと驚いたのは、賞金が二千万円という浮世離れした文学賞が、日本に存在していたということだ。
二千万円といえば、単行本を十万部かそこら売らないと回収できない金額だと思うが、それを新人作家育成のためにポンと払ってしまうとは、太っ腹な出版社だな‥‥と思っていたら、大賞を受賞したのは、第一回と今回だけ。水嶋ヒロは今回の賞金を辞退したそうだし、来年から賞金は十分の一の二百万円になるという(それでも芥川賞や直木賞の倍の金額だが)。あれこれ憶測が飛び交うのも無理はないけど、まあ、ポプラ社はポプラ社でいろいろ大変なのだろう。
個人的には、文学賞でハクをつけてデビューなんてことはせずに、普通に幻冬舎あたりに持ち込んで本を出してしまった方がよかったんじゃないかと思う。誰が書いた作品であろうと、結局、それに対する本当の評価を下すのは読者なのだし、たとえそこそこの部数しか売れなかったとしても、読んだ人の心にしっかりと残る作品であれば、それはそれで価値のあることだから。
そういう自分も、遠い昔、ノンフィクションの文学賞に応募したことがあったなあ。あの頃は‥‥本っっ当にヘタクソだった(苦笑)。どうにかしていっぱしの物書きになりたくて、でも何のチャンスも見つけられなくて、藁をもすがる思いで、あがいていたっけ。

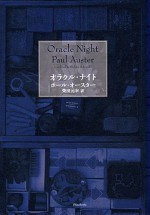 長編小説の醍醐味は、物語のめくるめく奔流に身を任せ、時を忘れて読み耽ることにあると思う。僕がこれまでに読んだポール・オースターの小説——「
長編小説の醍醐味は、物語のめくるめく奔流に身を任せ、時を忘れて読み耽ることにあると思う。僕がこれまでに読んだポール・オースターの小説——「