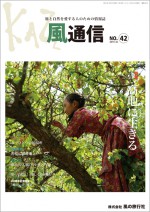終日、部屋で仕事。本の編集作業も、いよいよ本格的に忙しくなってきた。
編集の仕事を志してから、かれこれ二十年近くになる。地味で、単調で、せわしない作業のくりかえしだけど、何もないところから人の心を動かすものを作り出していくこの仕事が、僕はとても気に入っている。
ただ、自分が編集者としての資質を持ち合わせているかというと‥‥どうかな、と思う。
僕の知人には、周囲の誰もが認める優秀な編集者の方々が、何人もいる。その方々の仕事ぶりを見ていると、卓越したセンスとか、細部へのこだわりとか、疲れを知らない体力とか(苦笑)、そういった能力よりも、編集者にとって一番大切な資質は、周囲の人々とのコミュニケーション能力なのだと、つくづく思い知らされる。人間的に慕われている編集者さんは、間違いなくいい仕事を積み重ねている。
その点では、自分は本当に未熟だし、たとえば雑誌の編集長のように、大勢の人を取りまとめてチームとして動かしていく役割にはまったく向いてないと思う。どちらかというと「使う」よりも「使われる」立場の方がしっくりくるし、あるいは自分でできることはなるべく自分でやってしまう——企画・執筆・撮影・編集といったあたり——方が、力を発揮できるような気もする。
まあ、自分勝手なんだな、要するに(苦笑)。