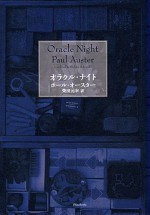 長編小説の醍醐味は、物語のめくるめく奔流に身を任せ、時を忘れて読み耽ることにあると思う。僕がこれまでに読んだポール・オースターの小説——「ガラスの街
長編小説の醍醐味は、物語のめくるめく奔流に身を任せ、時を忘れて読み耽ることにあると思う。僕がこれまでに読んだポール・オースターの小説——「ガラスの街 」をはじめとするニューヨーク三部作や「リヴァイアサン
」をはじめとするニューヨーク三部作や「リヴァイアサン 」「ミスター・ヴァーティゴ
」「ミスター・ヴァーティゴ 」「幻影の書
」「幻影の書 」といった作品群は、僕を心ゆくまで耽溺させてくれた。ところが、先日発売された「オラクル・ナイト
」といった作品群は、僕を心ゆくまで耽溺させてくれた。ところが、先日発売された「オラクル・ナイト 」は、それらとはちょっと趣向の違う作品だった。
」は、それらとはちょっと趣向の違う作品だった。
主人公シドニー・オアの職業は、やっぱりというか、またしてもというか、作家だ。彼が奇妙な文具店で見つけた青いノートに文章を書きはじめることで、いくつもの物語が動き出す。シドニーと妻のグレースと友人のジョン・トラウズとをめぐる物語。青いノートに綴られた、それまでの人生を捨てて行方をくらました男と、電話帳の図書館をめぐる物語。その物語の中で主人公に渡される、ある作家が遺した小説「オラクル・ナイト」。タイムトラベルをテーマにしてシドニーが書いた映画の脚本。ジョンが若い頃に書いた短篇「骨の帝国」——。こうした「物語の中の物語」を組み込むのはオースターが得意とするところだが、この本ではそれがさらに多層化していて、途中に注釈の形で何度も挿入される補足エピソードとあいまって、複雑な入れ子構造になっている。
そしてこれらのエピソードの大半は、意図的に結末を迎えることなく途切れてしまう。文具店の店主M・R・チャンの正体も、ポルトガル製の青いノートの謎も、答えを与えられない。シドニーとグレースを襲った一連の悲劇から現在へ至るまでの道程すら、途中でふっつりと途絶えてしまう。言葉は過去の出来事を記録するだけでなく、未来の出来事を引き起こす力も持っている。オースターはそのことを伝えたいがために、このように手の込んだ構成を選んだのかもしれない。それでいて全体が破綻することなくまとめあげられているのは、彼の技量があればこそだろう。
だが、正直に言うと、ちょっと読みづらかった。流れに引き込まれかけたところで、長い注釈でばっさりと寸断されたり、エピソードが途切れてしまったりするので、いいところで足元の梯子をポンと外されてしまうような違和感をたびたび味わうことになった。読者をグイグイ引き込む物語性という点では、この作品は弱いと思う。あと、シドニーとグレースとジョンをめぐるエピソードが、かなり序盤の段階から結末が透けて見えてしまっていて、終盤の展開が予想の範囲内だったことも、拍子抜けした要因かもしれない。そういったことも含めてオースターの計算のうちだったとすれば、それはそれでたいしたものだが。
次に邦訳される作品は、心ゆくまで物語に耽溺できるような、長編小説ならではの醍醐味を味わえるものだったらいいな、と思う。

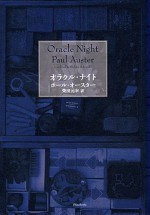 長編小説の醍醐味は、物語のめくるめく奔流に身を任せ、時を忘れて読み耽ることにあると思う。僕がこれまでに読んだポール・オースターの小説——「
長編小説の醍醐味は、物語のめくるめく奔流に身を任せ、時を忘れて読み耽ることにあると思う。僕がこれまでに読んだポール・オースターの小説——「