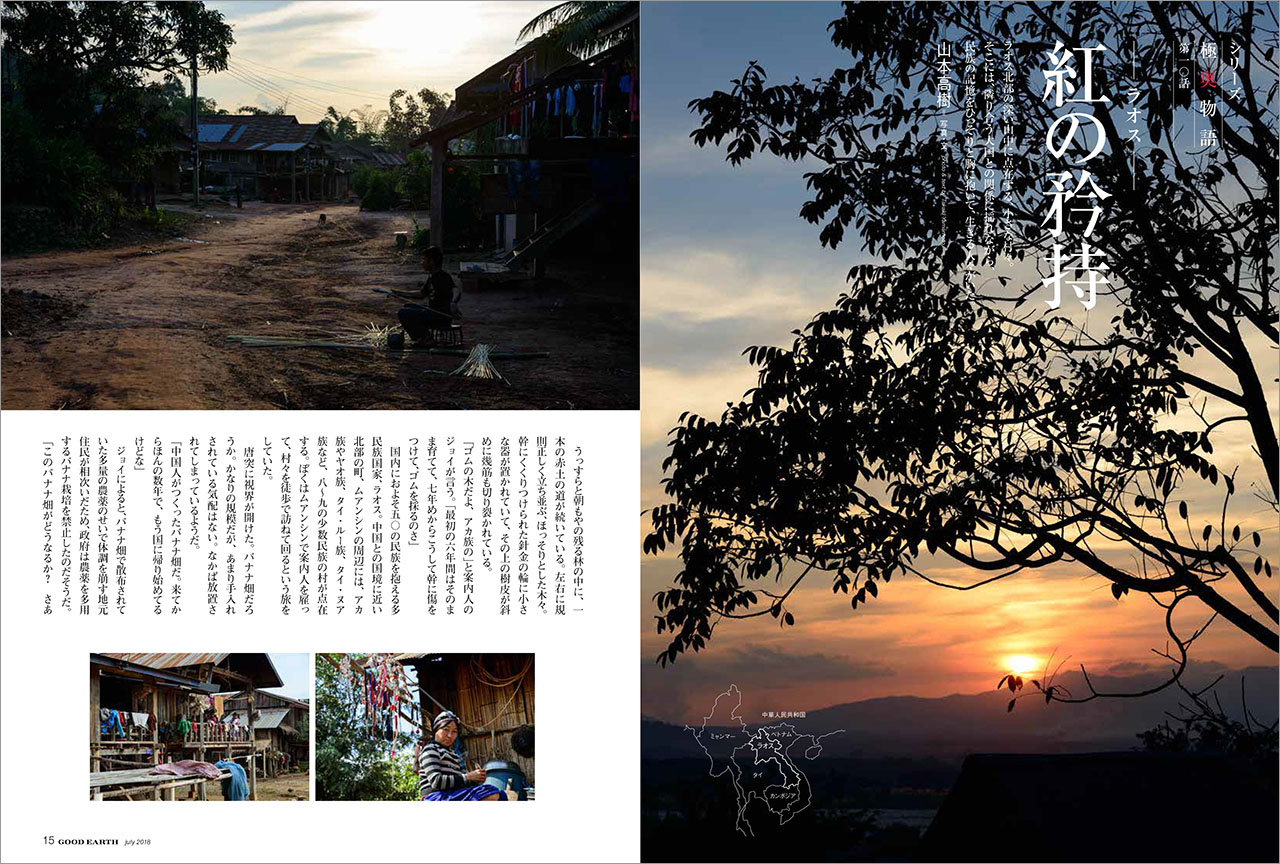この間の週末は、用事があって、一泊二日で神戸に行ってきた。
神戸では、元町というところで宿を取った。元町はほんのりと潮の匂いのする町で、広々とした商店街を、人々がのんびりと行き来していた。「神戸ビーフ」を謳う看板があちこちにあり、それと同じくらいの数のスパイダーマンの等身大人形が、なぜかあちこちに貼り付いている。元町にはこぢんまりとした中華街もあって、大勢の若者たちがわいわい騒ぎながら、小さな椀で売られている400円くらいの麺を道端ですすっていた。
宿はその中華街のすぐ近くにあった。シンプルで小綺麗な宿で、Wi-Fiはもちろん、フリーのドリンクバーもある。海外からの宿泊客も多いから、このくらいの設備はあって当然なのだろう。夕方に少し散歩した後、お茶でも飲もうと思ってそのドリンクバーに行くと、むっちゃ見覚えのあるパッケージの烏龍茶のティーバッグが置いてあった。海外の中華圏を旅すると、いろんなところで遭遇する、どこにでもあるありふれた烏龍茶。ありふれてるのに、これがまた、うまいのだ。
ティーバッグをお湯に浸して、ひと口すすったとたん、どこかの国の見知らぬ宿にいるような気分になった。