
トレッキングシューズといえば、僕はずっと長い間、キーンのターギーIIを履き続けてきた。キーンのラインナップの中でもド定番のこのモデル、履きやすさや歩きやすさは申し分ないのだが、難点は耐久性だった。しばらく履き続けていると、貼り合わせてあるソールの黒い部分とグレーの部分が、端からだんだんはがれて浮いてきてしまうのだ。まあ、ラダックやスピティくんだりで、岩だらけの灼熱の荒野を毎日何十キロも歩き続けるような使い方をしてる僕も悪いのだが(苦笑)。
そんなわけで、3足くらい買い換えてきたターギーIIに代わる新戦力として、同じくキーンのデュランド ロー WP
を導入することにした。ポートランドの自社工場で製造しているというこのモデル、ウリは耐久性だそうで、相当な距離のフィールドテストを経て製品化されたそうだ。ソールの構造も改良されているし、それ以外の部分の造りもがっしりしている印象。試しにこれで陣馬山や高尾山、御岳山を歩いてみたが、石ころがあろうが木の根があろうが、何も気にせずがしがし歩ける安心感があった。これならラダックでもたぶん大丈夫だろう。
このデュランド ロー WP、サイズ感はキーンの他の製品をほぼ一緒だと思うが、個人的にはターギーII
とフィット感がかなり違う(さらにぴったりくる)感じがしたので、購入を検討している人は、トレッキング用ソックスを持参して店頭で試し履きすることをおすすめする。あと、シューレースが結び方によってはややほどけやすいのではと思ったので、僕は最初からシューレースストッパーを使って締めている。
というわけで、新しい相棒、どうぞよろしく。

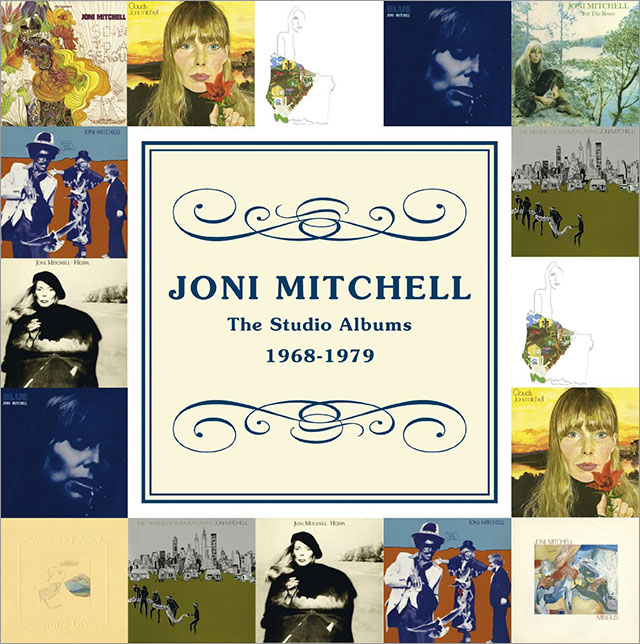

 先日のノルウェー取材の時に乗った飛行機では、なぜかインド映画のラインナップが充実していた。ミュージカルシーンがばっさりカットされた残念なものも多かったのだが、この「
先日のノルウェー取材の時に乗った飛行機では、なぜかインド映画のラインナップが充実していた。ミュージカルシーンがばっさりカットされた残念なものも多かったのだが、この「