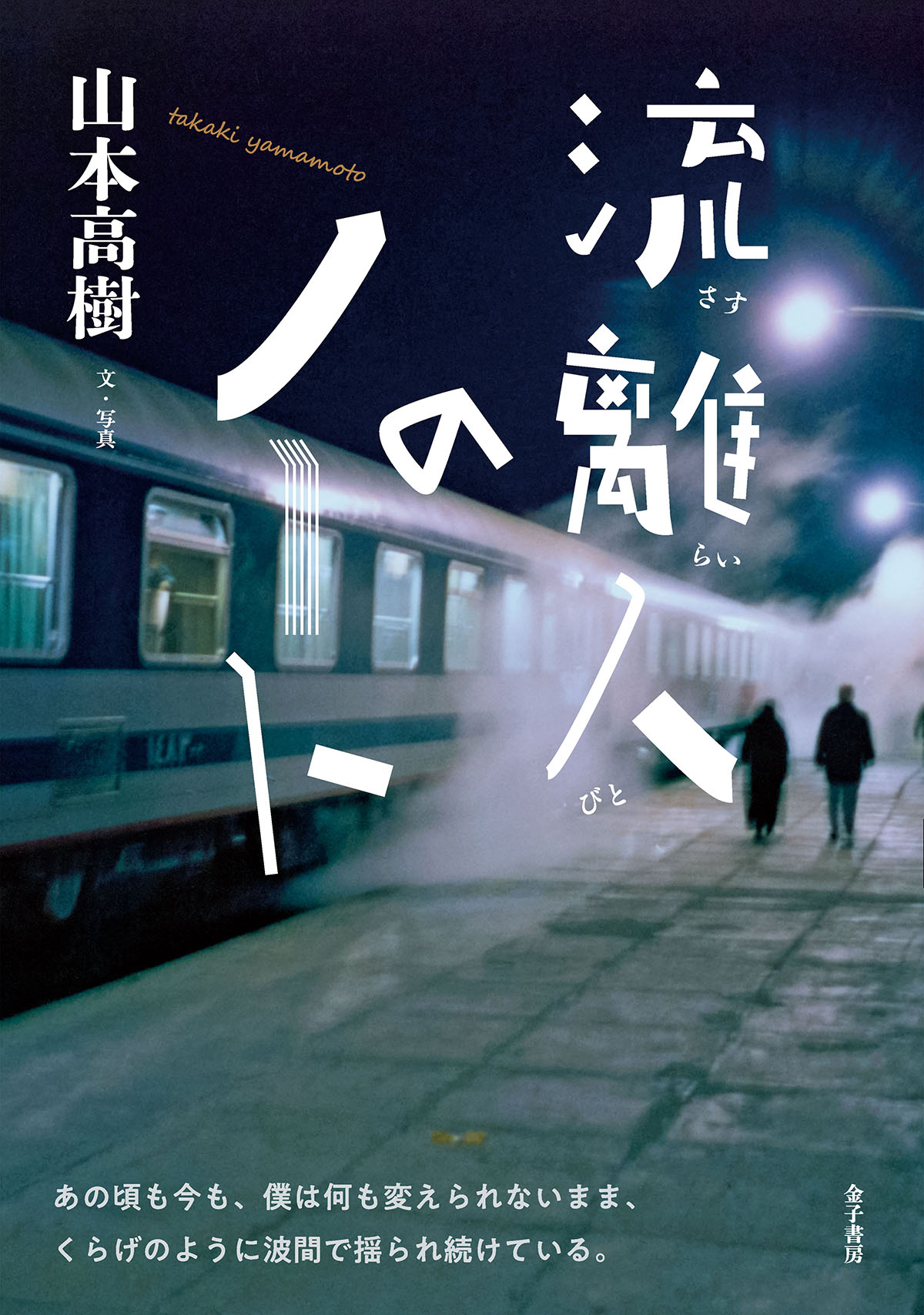二十年近く前から、ラダックのパンゴン・ツォをはじめ、世界各地にある鮮烈な風景の数々を舞台に撮影された「落下の王国」という映画がある、という話は聞いていた。当時は日本にいなかったし、その後も目にする機会はなかったのだが、最近になって、公開当時はカットされていたシーンを追加された4Kデジタルリマスター完全版が上映されはじめた。動員は予想以上に好調で、早々と興収1億円を突破したという。僕も、池袋の映画館でBESTIA上映される回を観に行ったのだが、平日の午後だったのに、ほぼ満席だった。
舞台は二十世紀初頭、米国のとある病院。オレンジの収穫中に木から落ちて腕を骨折した移民の少女、アレクサンドリアは、映画の撮影でスタントに失敗し、橋から川に落ちて下半身不随の大怪我を負ったロイと、ふとしたきっかけから話をするようになる。ロイはアレクサンドリアに、六人の勇者たちが悪者たちに立ち向かう冒険の物語を、思いつくままに語り聞かせはじめる。それは、彼女をうまく懐柔して、自分が命を絶つための薬を彼女に持って来させるためのものだったのだが、やがてその物語は壮大な叙事詩となり、アレクサンドリアだけでなく、人生に絶望した語り手のロイ自身にも影響を与えはじめる……。
ロイがアレクサンドリアに語り聞かせる物語は、彼が適当に思いつくままにしゃべる作り話で、時にはアレクサンドリアのリクエストも加わったりするので、辻褄もあっていない、奔放で、何でもありの空想世界になる。何でもありだからこそ、風景も衣装も演出も、すべてにおいて極限まで美を追求することが可能になる。秀逸なアイデアだ。最近の映画のように安易にCGなどに頼らない、実在する風景と俳優と衣装による圧倒的な美の表現が、観る人の心に刺さっているのだろう。
後にも先にも、こういう映画は、なかなかない。映画史に残る作品だと思う。