
10日間の南アフリカでの取材を終え、昨日の夜、日本に帰ってきた。
プレスツアー特有の窮屈さと時間のなさはあったものの、初めて訪れたアフリカ最南端の国での日々は、確かに得難い体験だった。特に旅の終盤、ピーランスバーグ国立公園で野生動物の姿を追いかけた二日間は、自分にとって良い経験になったと思う。
ジープで原野を走っている時、写真ではまともに撮れないほどはるか彼方を、ライオンの群れが獲物を追って全速力で駆けている姿を見た。別の場所では、ずっと以前に息絶えた後、ジャッカルやハイエナに肉も骨も食べ尽くされ、皮だけになったキリンの亡骸を見た。そこは動物園などではなく、命のやりとりが日々当たり前のように行われている自然の中なのだということ。そうした自然の掟が支配する中では、一人の人間は本当にちっぽけで無力な存在でしかないことを、身をもって感じた。
あの大陸の大地を、いつかまた、踏みしめる日が来るのかもしれない。

 デリーから成田までの機内では、2時間以上の大作ばかり観ようとすると時間が足りなくなるので、短めの作品も一つ入れた。それが「Finding Fanny」。インド映画にしては一風変わった作品という前評判は聞いていた。
デリーから成田までの機内では、2時間以上の大作ばかり観ようとすると時間が足りなくなるので、短めの作品も一つ入れた。それが「Finding Fanny」。インド映画にしては一風変わった作品という前評判は聞いていた。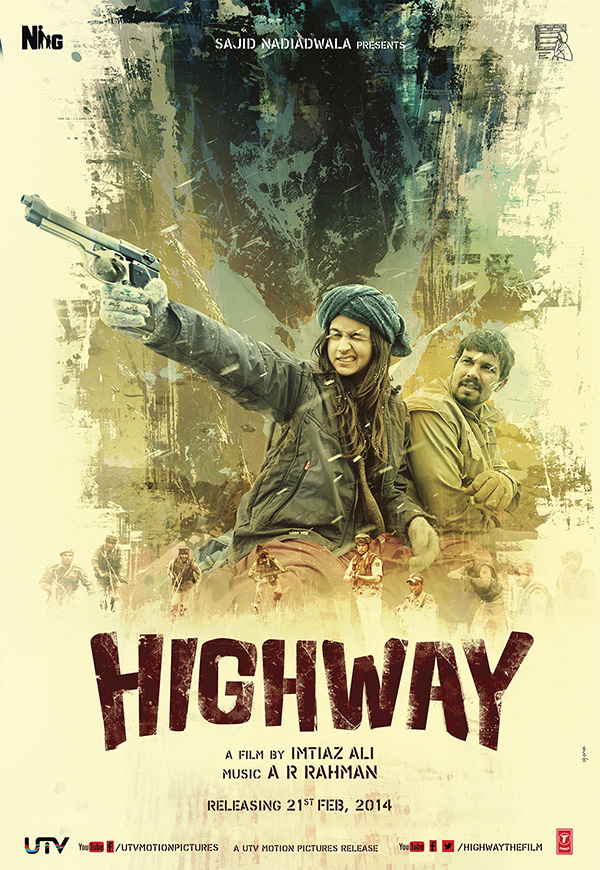 デリーから成田に戻るエアインディアの機内で観ようと決めていたのは「
デリーから成田に戻るエアインディアの機内で観ようと決めていたのは「 成田からデリーに向かうエアインディアの機内で観た2本目の映画は「
成田からデリーに向かうエアインディアの機内で観た2本目の映画は「