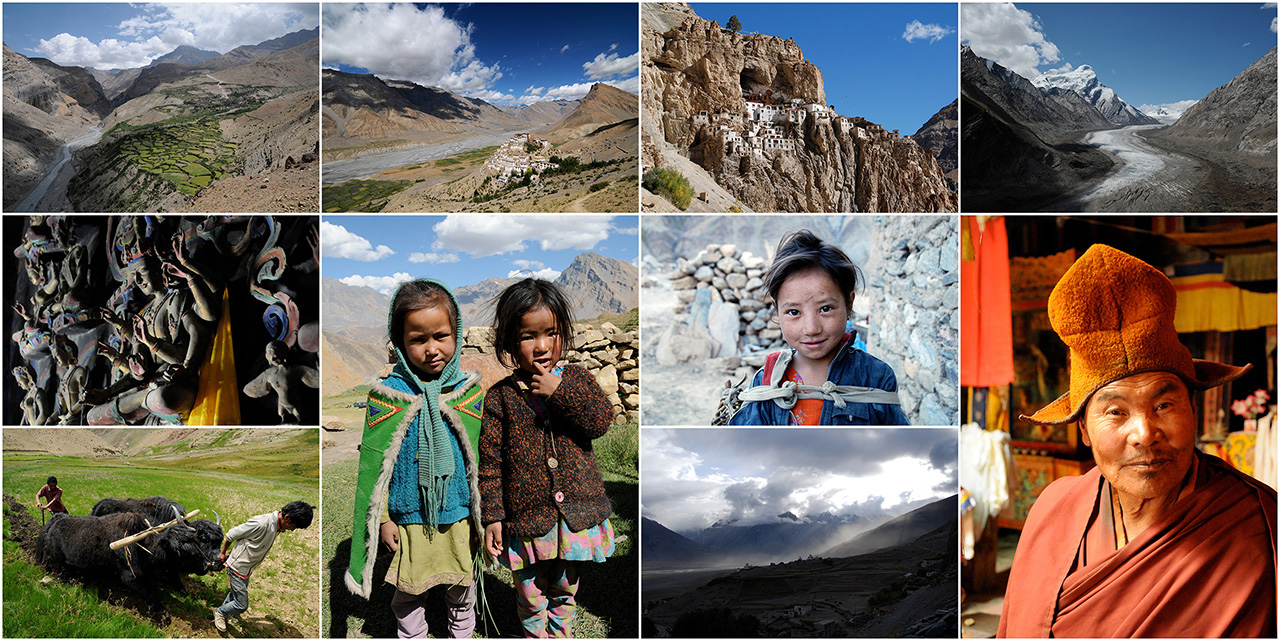日曜日、代々木公園で開催されていた、アースデイ東京に行ってきた。売店でサーモン&チップスを買い、クラフトビールを飲み、ぶらぶらと会場内を歩いた。
原宿側の会場入口の近くで、シリアのアレッポ石鹸が売られていた。長引く内戦の影響で、アレッポもひどい状況になっているそうだが、アレッポ石鹸自体は工場を別の場所に移して、どうにか生産を継続できているらしい。
ほとんど反射的に列に並び、がっしりした塊の石鹸を一つ、買った。まだ使ったことのない石鹸に対する興味も、もちろんあった。でも、それ以上に、買わずにはいられない、何かいたたまれないような気持があった。
アレッポ石鹸を一つ買ったところで、かの地で苦しむ人々にとっては、何の助けにもならないのかもしれない。でも、忘れないでいること、見て見ぬふりをしないことが、まずは大切なのかもしれない、とも思う。