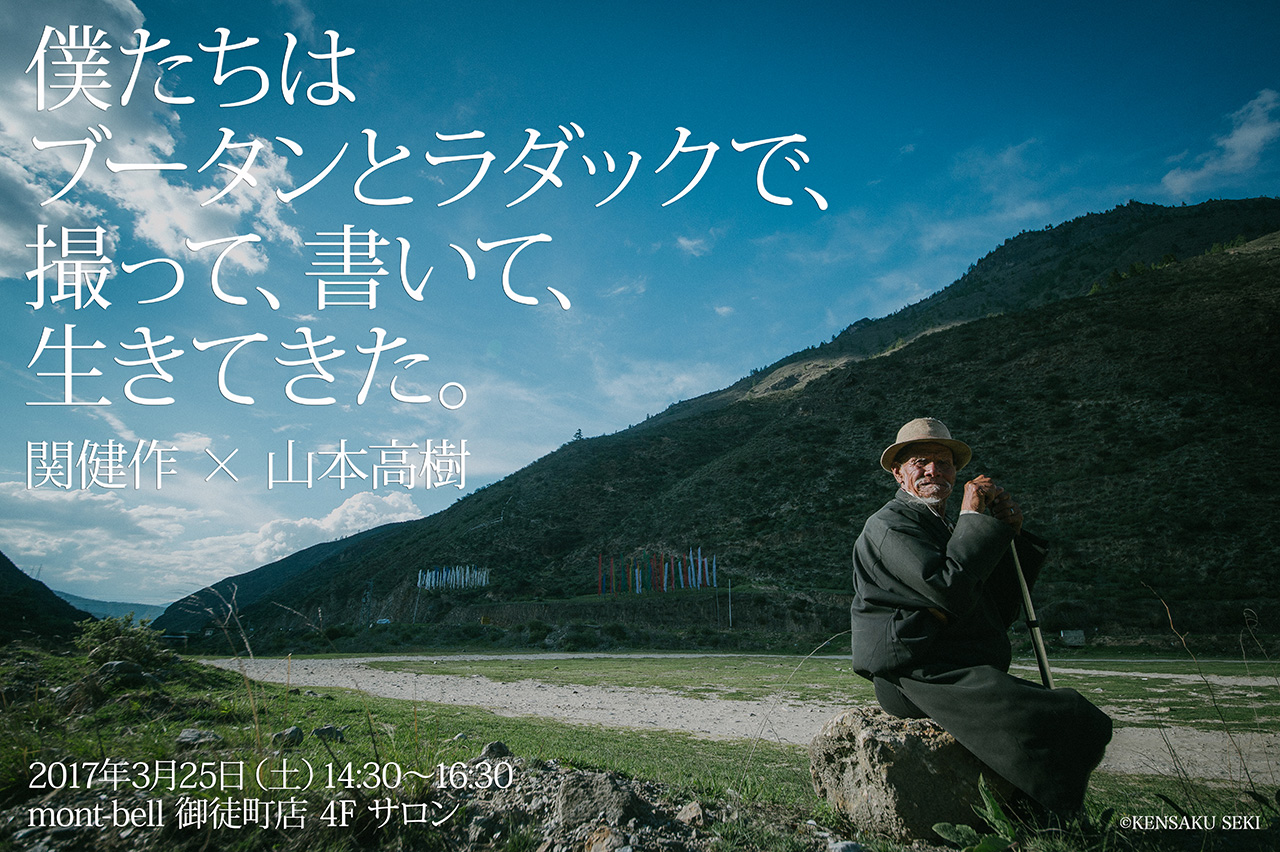明日から約1週間、再びアラスカに行く。
明日の夕方発の飛行機に乗り、シアトル経由でアンカレジへ。翌朝、鉄道に乗ってタルキートナという小さな町まで行き、そこからセスナに短時間乗せてもらって、原野のど真ん中にある湖に着氷(湖面は凍結しているから)。湖のほとりにあるロッジに数日間滞在し、スノーシューを借りて周辺を歩き回り、写真を撮る。
楽しみではあるのだけれど、同じかそれ以上に、怖い、という気持がある。半年前、南東アラスカのクルーゾフ島で味わった、あのぞわぞわするような感覚が、また甦ってくる。答えの見えない真っ暗な淵に佇み、飛び込むかどうか、逡巡するような……。いや、自分でもわかっている。飛び込むしかないのだ。たとえ結果がどうなろうとも。
帰国は14日(火)夜の予定。では。