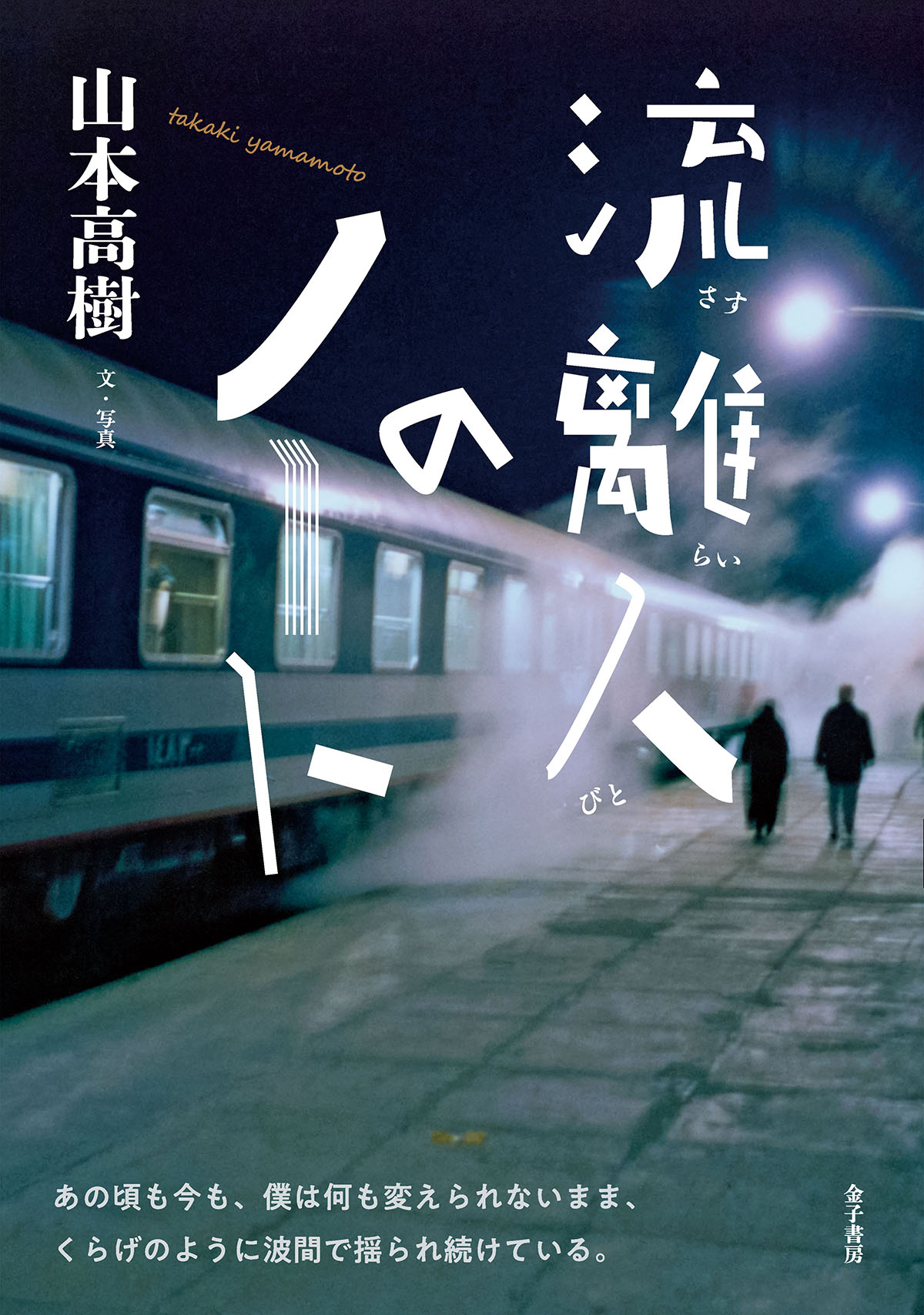ハーマン・メルヴィル『白鯨』上中下巻、読了。巨大な白鯨モービィ・ディックと隻脚のエイハブ船長の物語のあらましは、あまりにも有名なので子供の頃から知ってはいたが、原作自体を通読したことはなかった。しかし、まさかこれほどの「怪作」だとは、想像もしていなかった。
不安定にうつろう語り手、ツギハギのプロット、寓意に満ちた大仰な台詞、そして必要以上にテンコ盛りの鯨と捕鯨にまつわる(いささか上から目線の)うんちく。捕鯨船での自身の経験と寄せ集めた知識をありったけの情熱とともにぶち込んだ、メルヴィルの乾坤一擲の力作だったとは思うのだが、とにかく長いし、正直、途中から「何なんだこいつ……」と呆れながら読んでいた(苦笑)。
とはいえ、最終盤のピークオッド号とモービィ・ディックの激闘の描写は凄まじかったし、色んな意味で忘れられない読書体験にはなった。人生で一度くらいは、挑んでみてもいいかもしれない作品。
こういう、難解というか手強い大作に、今後も気が向いたらチャレンジしてみようかな。まだ読めていない古典の名作は、山ほどあるし。悪戦苦闘しながら読むのも、読書の愉しみの一つなのだろうし。