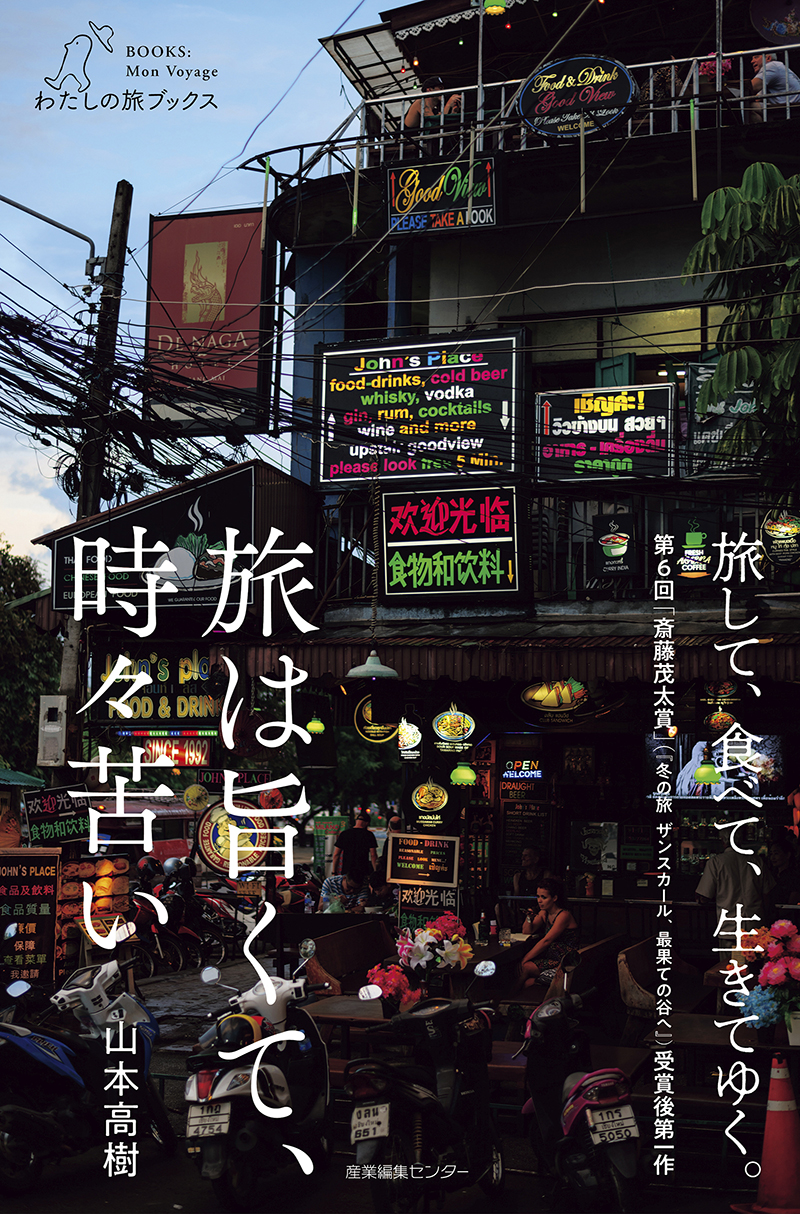午後、都心の出版社で打ち合わせ。制作中の本について、編集者さんと、あれこれ密談。
今作っている本については、このまま粛々と作業を進めていけば、初夏か晩夏かまだ定まっていないが、いずれにせよ、夏のうちには上梓できると思う。なので、これからしばらくはその作業に没頭するだけなのだが、僕自身には別の懸念事項がある。今年の夏の予定だ。
制作中の本のほかに、別の出版社と、ラダックについての本を作ることが決まっている。その本に必要な取材を今年の夏に実施して、秋以降に執筆に取りかかって、来年の前半くらいに完成できれば……という青写真を描いていた。
でも、最近のコロナ禍の再燃で、夏の海外渡航はすっかり不透明な状況になっている。不可能ではないかもしれないが、渡航のためにいろいろ無理をしなければならないかもしれず、しかも取材先の現地が平穏な状況に戻っている保証もない。正直、今年の夏の渡航は難しいかな、と思っている。
なので、その別の本に関しては、取材と執筆の順序を逆に組み替えようと考えている。先にできる範囲で執筆をしておいて、取材は来年の夏に回し、その成果を反映させて、来年のうちに完成させる、というやり方だ。内容的に先にある程度執筆できる本ではあるので、今はそれがベストな選択肢かなと思っている。
まあ、できる時に、できることを、粛々を進めていくしかないのかなと思う。
———
ハワード・ノーマン『ノーザン・ライツ』読了。カナダの北極圏に暮らす少数民族の口承物語を取材していた著者が、自身の少年時代の経験を反映させながら書いた最初の小説作品。中盤から終盤にかけて結構な急展開の連続で、個人的にはそのチェンジオブペースにちょっと驚いてしまったのだが、序盤で描かれた辺境の村クイルの情景と、そこで暮らす人々一人ひとりの描写は本当に緻密で豊かで好ましくて、一冊丸ごとクイルが舞台でもよかったのに、とすら思ってしまった。主人公のノアには、いつかクイルに戻ってほしかった、かも。
———
佐々木美佳『タゴール・ソングス』読了。十日ほど前、同書の刊行記念に催された、佐々木さんが監督したドキュメンタリー映画『タゴール・ソングス』上映会&トークイベントに参加して、会場で購入した。映画の字幕でも、この本でも、タゴールの遺した数々の歌を佐々木さんが自ら訳した歌詞が載っているのだが、その言葉選びの一つひとつがとても丁寧で、するっとタゴールの歌の響きに感情を重ねることができた。ある土地や人々に対して、予断を何も持たず、まっさらな気持ちでまっすぐに向き合うのは、ノンフィクションの基本であると同時にもっとも難しいことでもあるが、佐々木さんは、映画でも本でも、そのまっすぐな姿勢にぶれがない方だなあ、と感じた。誠実な映画だったし、誠実な本だと思う。