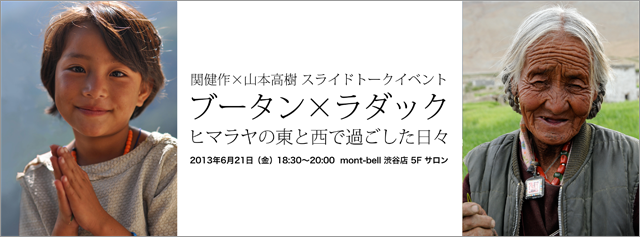一口に編集者といっても、いろんなタイプの人がいる。たとえば書籍の編集者なら、著者の企画や原稿をそのまま活かす形で仕上げる人もいれば、著者と侃々諤々やりあって書き直しを重ねながら仕上げていく人もいる。
僕の場合、自分が著者の立場の時に、書き上げた原稿の内容自体に編集者からダメ出しされたことはほとんどない。何でかなと思い返してみると、それはたぶん、「ダメ出しされての書き直し」という無駄な手戻りが起きないように、編集者が各段階に至るまでの道筋をわかりやすく示してくれていたからだと思う。
「どういう本にするか」という完成形のイメージを決め、全体の構成案を丁寧に詰めていって、試し書きをして文体やトーンを調整しながら、少しずつ書き上げていく。その各段階で編集者に細かく確認をしてもらって、イメージを共有するのが、無駄な手戻りを防ぐためには大切だと思う。もちろん、草稿が書き上がってからも、第二稿、第三稿と書き直しをしていく場合もあるが、それは「ダメ出しされての書き直し」ではなく、明らかに目的があって、さらに精度を上げていくための書き直しだ(込み入った表現をわかりやすくする、など)。無駄な手戻りをくりかえしていては、そういう精度の向上を検討する余裕もなくしてしまう。
著者と侃々諤々やりあうタイプの編集者を否定するつもりはないが、個人的には、そういう風になってしまうのは、著者と編集者の間で完成形のイメージをうまく共有できていないからではないか、と思う。著者が完成形のイメージに近づくための作業をスムーズに進められる道筋をつけてあげるのが、僕が理想とする編集者の役割。自分自身が編集者の立場の場合も、そうありたいと思う。‥‥まあ、それでもいろんな事情が絡んでくるので、なかなか一筋縄ではいかないのだけれど(苦笑)。